
大学の「中退」「退学」「除籍」は何が違う?
大学を辞めることを考えたとき、真っ先に気になるのがこの3つの言葉。
でも、いざ調べてみると似たような説明が多く、「結局どう違うの?」とモヤモヤしてしまう人も多いはずです。
- 「退学届を出さずに行かなくなったらどうなるの?」
- 「除籍になったら、履歴書にはどう書けばいい?」
- 「中退って就職に不利って聞いたけど、本当なの?」
そんな疑問や不安を抱えたまま時間だけが過ぎていくのは、精神的にもかなりツライですよね。
実は、中退・退学・除籍には意味も手続きも、そして就活への影響も大きな違いがあります。
どの方法を選ぶかによって、将来受けられるサポートや証明書の発行の可否も変わってくるため、安易な判断は避けるべきです。
この記事では、それぞれの違いを整理しながら、あなたの状況に合わせた適切な選択ができるように、必要な情報を一つずつ丁寧に解説します。



「あのとき、ちゃんと調べておいてよかった」
そう思えるように、今ここで正しい知識を持っておきましょう。
中退・退学・除籍の違いをまず理解しよう


大学を辞めるときに使われる「中退」「退学」「除籍」という言葉は、意味が似ているようで実はまったく違います。
混同したまま進めてしまうと、証明書の発行ができなかったり、就活で不利になったりと後悔の原因になりかねません。
違いを一言で表すと、「中退と退学は自分の意思、除籍は大学の判断」。
この違いが、履歴書の書き方や再入学の可否、就職活動への影響など、あらゆる場面で差を生むのです。
まずは、それぞれの意味を正しく理解することから始めましょう。



ここを押さえるだけで、あなたが取るべき選択がグッと見えてきます。
「中退」「退学」「除籍」の意味と定義の違い
この3つの言葉はすべて「大学を辞める」という結果を指していますが、辞める理由や手続き、主体の違いによって意味が大きく異なります。
まず「中退」は「中途退学」の略で、学生本人の意思で途中で辞めることを指します。
進路変更や経済的理由、体調不良など、自主的な判断で大学を離れるケースです。
退学届を出し、大学側が正式に承認すれば中退となります。
一方「退学」は、実は中退とほぼ同義で使われる場合が多く、大学によって呼び方が異なることもあります。
ただし、学校側からの勧告や指導の一環で「退学」を勧められることもあるため、若干ニュアンスが変わることもあります。
そして「除籍」は、学生の意思とは関係なく大学側が学籍を抹消する処分です。
学費未納や単位不足、在学期間の超過、問題行動などが主な理由です。手続きを怠って放置していると、自動的に除籍されることもあります。
- 中退・退学=自主的な選択
- 除籍=大学側からの処分
この違いが、のちに必要となる証明書の発行や、就活・進学での扱いに大きく関わってくるのです。
なぜ混同されやすい?「中退」と「退学」の関係
「中退」と「退学」は、よく似た意味で使われています。
大学や情報サイトによっても定義が違うため、混同されやすいのが実情です。
たとえば大学では、書類上は「退学届」と記載されていても、本人は「中退しました」と話すことがよくあります。
これは、手続きと表現にズレがあるからです。
一般的には、大学を途中で辞めたことを「中退」と呼び、実務的な処理は「退学」扱いにしている大学も少なくありません。
一方で、「中退=自己都合」「退学=処分」というイメージを持つ人もいます。
でも実際は、どちらも本人の意思による自主的な退学です。
誤解されやすい理由のひとつが、「退学処分」という別の言葉の存在です。
さらに一部の大学では、「退学」を除籍的な意味で使っている場合もあります。
だからこそ、自分が通う大学ではどう定義されているのかを確認することが大切です。
言葉の印象に振り回されず、正確に把握することが、就活や手続きの安心につながります。
除籍は処分?他の辞め方との決定的な違い
除籍は「大学を辞める」という意味では中退や退学と共通していますが、最大の違いは“処分としての性質”を持つことです。
中退や退学は、自分の意思で「辞めたい」と申し出て手続きを行います。
たとえば、体調不良や家庭の事情、学業への意欲低下など、背景はさまざまですが、あくまで本人主体の選択です。
一方、除籍は違います。大学側の判断で一方的に学籍が抹消される措置です。
学費未納、在学年数の超過、単位不足など、大学の規則に違反する状態が続いた場合に適用されます。
学生側が何もしなくても「通告なしに除籍」というケースもあるため、放置は危険です。
また、除籍になると大きな問題が1つあります。
それは、証明書類(在学証明・成績証明など)が発行されない可能性があることです。
退学届を提出していれば卒業見込み証明や成績証明書を受け取れる場合もありますが、除籍ではそれが難しくなり、就職活動や転入学に支障が出る可能性があります。
除籍は「もう一度大学に入り直す」際にもハードルが高くなります。
大学によっては除籍理由を精査されたり、入学許可が下りにくくなったりするからです。
このように、除籍は本人の意志では避けられないリスクが多く、進路に大きな影響を与える処分であるという認識が必要です。
それぞれの手続きの流れと必要書類
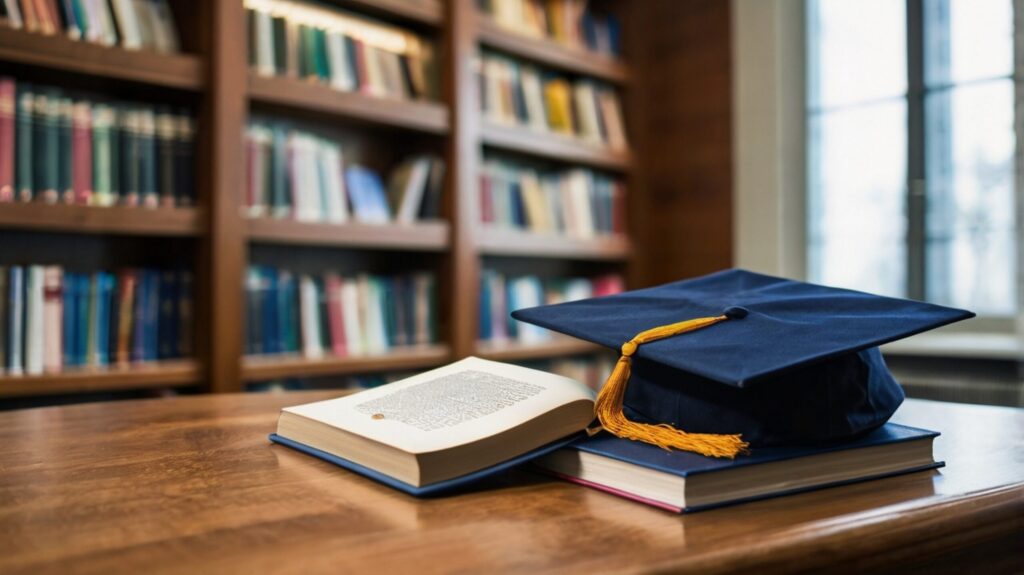
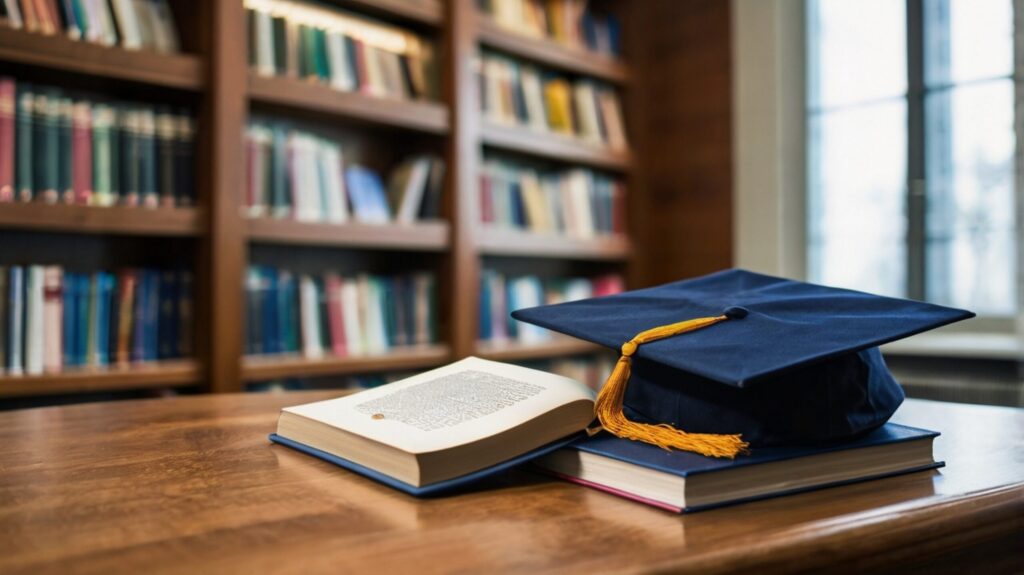
大学を辞めるには、形式に応じた正しい手続きが必要です。
中退や退学は自分から申請するものですが、除籍は大学側が判断するため、準備できることも異なります。
ここでは、各ケースごとの基本的な流れと必要書類を整理しておきます。
- 中退(中途退学):退学届を提出し、教員・保護者との確認を経て大学が承認
- 退学:中退とほぼ同じだが、学校によって名称が異なるだけの場合もある
- 除籍:学費未納や単位不足などが原因で、大学側から一方的に学籍を抹消
- 中退・退学:退学届、身分証、学生証、場合により保護者の同意書
- 除籍:学生側の提出物は原則なし(通知は大学から届く)
中退・退学の基本的な手続きとは?
中退や退学を選ぶ場合、まずやるべきことは大学への正式な意思表示です。
黙って通わなくなると除籍扱いになる可能性があり、証明書が出なかったり、後々の進路に影響するリスクが高まります。
基本的な流れとしては、まず学生課などの窓口で退学届のフォーマットを入手します。
次に指導教員との面談や、保護者の同意書が求められる場合もあります。
これらを揃えた上で、大学側に書類を提出し、承認されることで正式に「退学」となります。
手続きをスムーズに進めるためには、辞める理由を明確に説明することと、書類の不備を避けることが大切です。
また、退学が承認されると「退学証明書」「成績証明書」などが発行され、就職や編入学の際にも使えるようになります。
「とりあえず休もう」と先延ばしにせず、明確な手続きを取ることが、今後の進路を考えるうえでも最も確実な方法です。
- 学生課で退学届を受け取る
- 指導教員との面談(理由の確認)
- 保護者の同意書(必要に応じて)
- 大学へ提出し、承認を待つ
- 承認後、証明書を受け取る
除籍になると何が起きる?自分でできる対応は?
除籍は、大学側の判断によって一方的に学籍が抹消される制度です。自分で辞める意思を伝える中退や退学とは違い、放置していた結果として“気づいたら除籍されていた”という人も珍しくありません。
主な理由には、学費の未納や単位不足、在籍年数の超過などがあります。
大学から通知が届くこともありますが、連絡がつかずにそのまま処分となることもあります。
除籍になると、在学証明書や成績証明書が発行されない可能性がある点が最も大きな問題です。
履歴書に学歴を正しく記載することが難しくなったり、再入学や転入学の際にも不利に働くことがあります。
ただし、状況によっては除籍を回避できることもあります。
学費の分割相談や再履修の申請、事務課との面談など、早い段階で行動することがカギです。
「どうせもう無理かも…」と諦めず、まずは大学に連絡し、自分の状況がどうなっているのかを確認するところから始めましょう。
- 学費未納ならまずは事務課に相談(分割納入の提案)
- 単位不足なら再履修や学習計画の再調整を検討
- 体調不良や家庭の事情なら、休学制度の活用を検討
- 大学の担当部署に早めに連絡し、状況を確認
- すでに除籍通知が届いた場合は、証明書の発行可否を確認
就職活動への影響はどこに出る?


大学を辞めたあと、最も不安になるのが就職活動への影響ではないでしょうか。
「中退は不利?」「除籍だと採用されにくい?」そんな疑問を持つのは当然です。
実際には、中退・退学・除籍のどれであっても、中途で大学を辞めたこと自体は共通しており、企業からはその理由と本人の誠意ある説明が重視されます。
しかし、履歴書の書き方や証明書の有無など、見えない部分で差が出やすいのも事実です。
このあとの見出しで、就職におけるそれぞれの辞め方の違いを詳しく見ていきましょう。
中退と除籍、企業が見るポイントの違い
企業が中退や除籍に注目するのは、「辞めたこと」そのものよりも、その理由や姿勢です。
たとえば中退なら、自分で決断して、必要な手続きをちゃんと済ませている。
その点は「計画的に動いたんだな」と、プラスに受け取られることもあります。
一方で除籍は、「授業に出てなかったのかな?」「ルールを守れなかったのかも…」というように、マイナスに受け取られる可能性があるのも正直なところです。
特に学費の滞納や、単位が足りないまま放置していた場合は、「自己管理が苦手?」と思われやすくなります。
でも、だからといって採用のチャンスがなくなるわけではありません。
企業が見ているのは、「そこから何を学んだか」「次にどう生かすか」。
つまり、ちゃんと説明できるかどうかがカギとなります。



だからこそ、面接では正直に、そして前向きに話せる準備をしておくことが大事ですね。
中退と除籍の企業側の見え方比較
| 項目 | 中退 | 除籍 |
|---|---|---|
| 主体 | 本人の意思 | 大学側の処分 |
| 印象 | 自主性・計画的な判断とされやすい | 放任・管理不足と見なされることも |
| 証明書の発行 | 基本的に可能 | 大学によっては発行不可 |
| 説明のしやすさ | 明確な理由を伝えれば好印象につながる | 正直に話せば評価される余地あり |
| 就職活動での対策 | 前向きな理由と今後の意欲をアピール | 誠実な説明+改善の意思を示すこと |
履歴書の正しい書き方と印象を悪くしないコツ
中退や除籍の経歴があると、履歴書にどう書くべきか悩んでしまいますよね。
特に「除籍」と明記するべきかどうかは、多くの人が迷うポイントです。
まず大前提として、履歴書には“事実を正しく、誤解を生まない形で書く”ことが重要です。
法律上、「中退」と書くか「除籍」と書くかに明確なルールはありません。
除籍であっても「中途退学」と記載することが一般的で、問題視されることはほとんどありません。
また、記載の際は辞めた理由を明確に補足するのがおすすめです。
たとえば「経済的理由のため中途退学」や「家庭の事情により中途退学」といった一文を添えることで、ネガティブな印象をやわらげることができます。
企業は学歴そのものよりも、「どう行動したか」「何を学んだか」「今後どう成長したいか」を重視します。



だからこそ、履歴書では事実を正直に書いた上で、自分の姿勢を表現することが大切です。
- 除籍でも「中途退学」と記載すればOK(法的問題なし)
- 辞めた理由を一言添えると好印象につながる
- 学部・学科名も省略せず、在学期間を明記する
- 中退時期が短くても省略せず、正確に記載する
- 書類審査よりも、面接での説明を意識した準備を
面接で聞かれる「なぜ辞めたのか」への答え方
中退や除籍の経験がある人にとって、最も緊張するのが面接での「辞めた理由」の質問です。
企業の採用担当者も、この点には必ず注目しており、ここでの受け答え次第で印象が大きく変わります。
大切なのは、辞めた理由を事実ベースで簡潔に説明したうえで、前向きな学びや意志につなげることです。
たとえば、
「体調を崩してしまい継続が困難でしたが、現在は改善しており再スタートを切っています」
といったように、過去の出来事と現在の状況、そして未来の展望をバランスよく伝えると説得力が生まれます。
除籍の場合は、やや説明が難しいですが、正直に背景を語りつつ、
「この経験から責任の重さを痛感し、現在は生活習慣や計画の立て方を見直している」
といった反省と成長をセットで伝えることが大切です。
企業が求めているのは、「辞めてしまった過去があるかどうか」ではなく、辞めたあとの態度や行動です。
マイナスをゼロにするのではなく、「学び直した」「働く意味を再認識した」など、ゼロをプラスに変えるような視点が評価されます。
無理に取り繕ったり、美談にする必要はありません。
等身大で、誠実に、そして前を向いているかどうか。



それが、面接で信頼を勝ち取る最大のコツです。
証明書の発行と学歴の扱いに注意
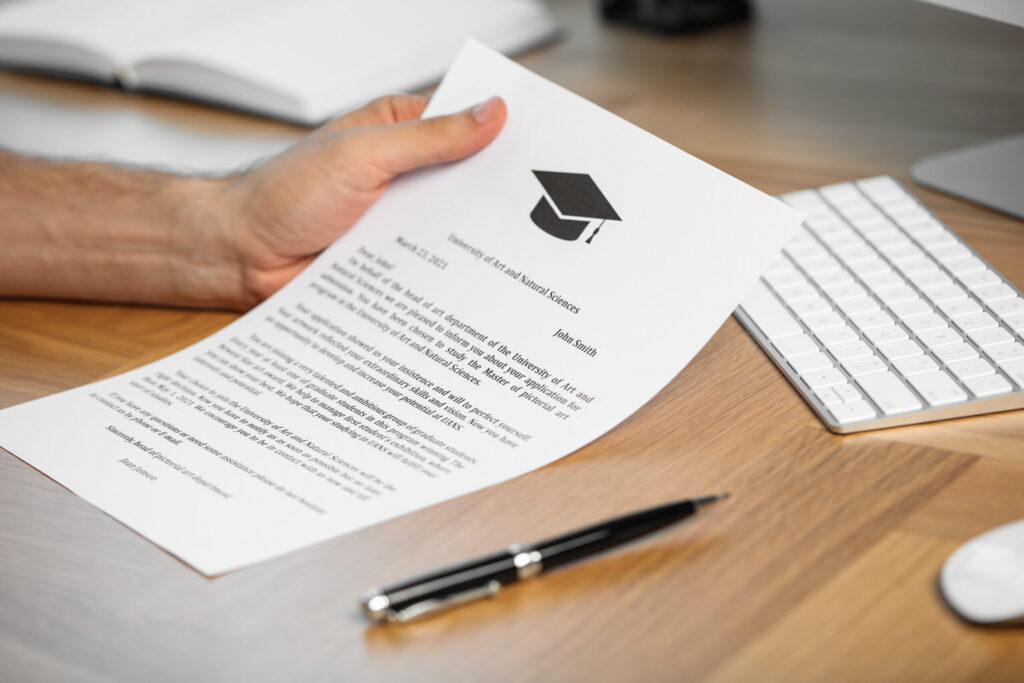
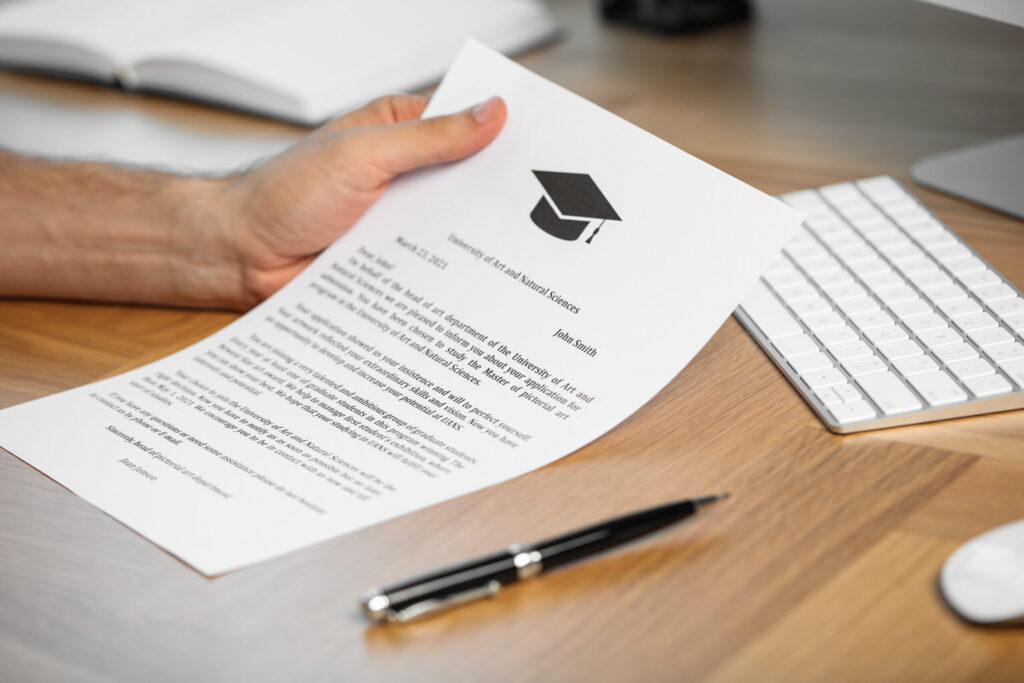
中退や除籍をするとき、意外と見落とされがちなのが証明書の発行と学歴の取り扱いです。
手続きの内容によっては、在学証明や成績証明書が取得できなくなり、就職活動や進学で困るケースもあります。
また、大学を卒業していない場合、最終学歴は「高校卒業」扱いとなります。
「大学中退」や「除籍」はあくまで経歴であり、学歴としては認められません。
このセクションでは、証明書の可否や学歴の書き方について具体的に解説していきます。
除籍だと証明書はもらえないって本当?
結論から言うと、除籍になると大学によっては証明書の発行が制限される可能性があります。
これは多くの人にとって盲点であり、「いざ必要になったときに発行できなかった」というトラブルも少なくありません。
中退(退学届を出して正式に手続きしたケース)の場合は、在学期間の記録が残るため、「在学証明書」「成績証明書」「退学証明書」などが問題なく発行されます。
これらは就職や編入、資格取得などに活用できます。
一方で除籍は、学費未納や単位不足といった理由で“規定違反”により大学を離れた状態です。
この場合、大学が「成績証明書の発行対象者ではない」と判断するケースがあります。
特に、学費を未納のまま除籍された場合、証明書発行を拒否されることもあり、事実上の“学歴が証明できない状態”に陥るリスクがあります。
「大学に通っていたことを証明できない」という状況は、履歴書や職務経歴書にも影響します。
就活で不自然な空白期間を生まないためにも、除籍前に自分の学籍状況と発行可能な証明書の種類を確認することが非常に重要です。
不安な場合は、学生課や教務課に「今のままでは除籍になりますか?」「証明書は出してもらえますか?」と早めに相談しておくのが安心です。
最終学歴はどうなる?履歴書での書き方も解説
大学を中退したり、除籍になった場合、「最終学歴はどうなるの?」と不安になる方も多いですよね。
実は、どちらのケースでも正式な最終学歴は「高等学校卒業」となります。
たとえ大学で3年学んでいても、卒業していなければ大学卒にはなりません。
「大学中退」「大学除籍」というのは学歴ではなく経歴扱いとなるため、履歴書では“学歴欄”に記載する際の表現に注意が必要です。
たとえば、以下のような書き方が一般的です。
- 令和〇年〇月 〇〇大学 △△学部 △△学科 入学
- 令和〇年〇月 〇〇大学 △△学部 △△学科 中途退学(家庭の事情により)
除籍であっても「中途退学」と書くことは可能ですし、実際にそう表記している方も多いです。
法律的なルールはなく、企業に誤解を与えず、事実に即した記述ができていれば問題ないとされています。
ただし、空白期間ができると採用側の不信感につながるため、理由の補足は丁寧に書くことがポイントです。
過度にネガティブな印象を与えず、正直で前向きな姿勢が伝わるように意識しましょう。
「学歴=高校卒業、でも大学に在籍していた事実も伝える」
このバランス感覚が、履歴書記載のコツです。
よくある不安とその対処法
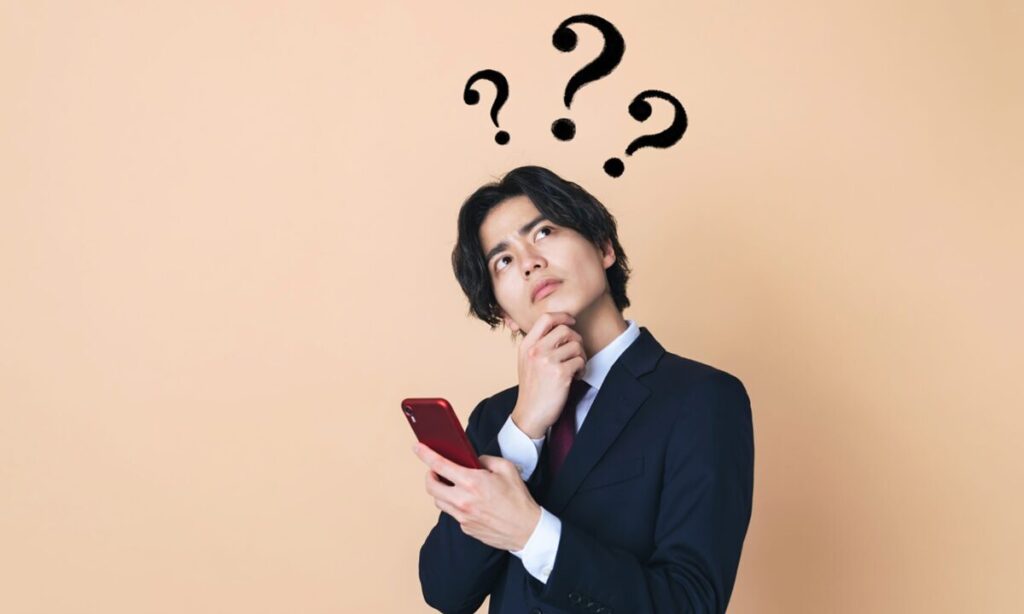
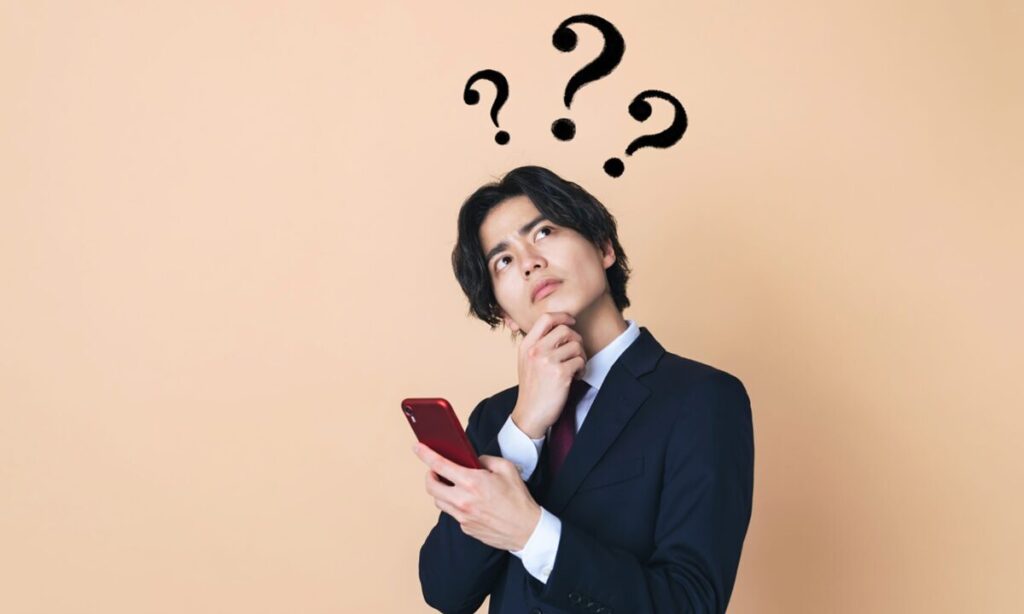
大学を中退・除籍した人や、これから辞めることを検討している人は、誰しも将来への不安や迷いを抱えるものです。
「この選択で本当に大丈夫?」「就職できるのかな?」と、自信をなくしてしまうこともありますよね。
でも大丈夫。よくある不安にはきちんとした対策や考え方があります。
このセクションでは、特に多い2つの悩みについて、現実的な視点で解決策をご紹介していきます。
「除籍になりそう」な時にやるべきこと
「学費を滞納してしまった」「単位が足りない」「気づいたら在学年限を超えていたかも…」
そんな状況で頭をよぎるのが「もしかして除籍になるのでは?」という不安ですよね。
結論から言うと、除籍のリスクは“放置”によって大きくなります。
逆に、早めに動けば回避できる可能性は十分にあります。
除籍は大学側の判断によるものですが、状況に応じた相談や手続きによって、休学や猶予などの選択肢が与えられるケースも多いんです。
まずは焦らず、以下のような行動を1つずつ取ってみましょう。
特に「まだ通知が来ていない段階」なら、あなた自身が選択できる余地は大きいですよ。
除籍リスクを感じたときにやるべき5つのこと
除籍のリスクを感じたときは、できることを一つずつ確認し、行動に移すことが大切です。
次の5つは、できるだけ早めに取り組んでおきたい対処法です。
- 学生課や教務課に相談する
- 学費の納入計画を立てて提案する
- 成績・単位状況を見直す
- 体調や精神的な問題がある場合は休学を検討する
- 家族と状況を共有する
「除籍されるかも…」と感じたときこそ、行動するチャンスです。
早めに動くことで、選択肢が広がる可能性は大いにあります。
家族や周囲への説明はどうする?
大学を辞めるときに、もうひとつの大きなハードルになるのが「家族や周囲への説明」です。
特に中退や除籍の場合、「がっかりされるかも」「ちゃんと話せる自信がない」と感じて、話し出せずに時間だけが過ぎてしまう人も多いです。
でも、実際にはしっかり向き合って話せば理解を得られるケースがほとんどです。
一番大事なのは、「辞めたこと」ではなく「辞めたあと、どうするか」という部分です。
たとえば「自分に合った道を見つけたから」「体調や環境が整わなかったけど、今は改善して再出発したい」など、前向きな理由や今後の行動をセットで伝えると、家族も安心しやすくなります。
もし除籍になってしまった場合でも、「放置していたことを反省している」「今は計画を立てて次に向けて動いている」といった変化の姿勢を見せることがポイントです。
誰だって迷ったり、立ち止まったりすることはあります。
だからこそ、自分の状況と真剣に向き合っている姿は、必ず相手に伝わります。
「怒られるかも」ではなく、「理解してほしい」と思って話してみてください。



あなたの言葉で、自分の道を説明することが、きっと信頼につながります。
まとめ:大学の「辞め方」は、将来を左右する大事な分岐点


中退、退学、除籍――呼び方は違っても、どれも大学を途中で離れるという点では同じです。
ですが、この3つには意味も手続きも違いがあり、それによって将来の選択肢も変わってきます。
中退や退学は、自分の意思で動くことが前提です。
手続きを済ませれば、必要な証明書も出してもらえます。
除籍は少し事情が違います。
大学側の判断で籍が外されるため、証明書が出ないケースもあり得ます。
そして、就職活動や転職活動で本当に大事なのは「どう辞めたか」ではなく、そのあとどう動いたかです。
たとえ中退や除籍だったとしても、伝え方ひとつで印象は大きく変わります。
大学を辞める決断は、たしかに大きな転機です。
でも、そのあとをどう進むかで、自分の道はいくらでもつくり直せます。



「辞めたことを引きずるより、これからのことを考えてみましょう!









